

DAN TOMIMATSU | 2021
Interview
DAN TOMIMATSU
まず初めに、なぜ僕がジュエリーをデザインしているのかというのをお伝えしたいと思います。
ジュエリーってはっきり言って何かの役に立つというものではないじゃないですか。服であれば、そもそもは体温調節とかそういう機能があるわけですよね。ジュエリーって全く何かの役に立つというものではない存在ですよね。
僕はプロダクトデザイナーとして役に立つものをデザインして勉強してきたんですけれども、その中で役に立たないと言われているものでも実は物理的にはそう見えるだけで、精神的に捉えてみると、実は人が生きていく上で、エッセンシャルな存在もあるのではないかと気付きました。衣服にもそういう側面はあると思うんですけれども、ジュエリーには純粋にその機能しかないんですね。
身に付けてどういう気持ちになるだとか、形が綺麗だと思えるとか。なので、ジュエリーというのはその時代の美しいと思われるものとか、何に価値があるのかという象徴物として存在していると思うんですね。
大きな枠で言うと人間は、金に価値があると思って身につけてきたわけですが、近代ではコンテンポラリージュエリーというジャンルがあるんですが、金やダイヤモンドなどに価値があることは当然わかっているんですが、それ以外のものにも価値があるんじゃないかと考える流れがありました。
ダンボールとか木とかそういう他の素材のものでもジュエリーになるんじゃないかという考え方です。DAN TOMIMATSUはその中間ぐらいに位置しながら、私たちの生活には何が大切なのかを模索しています。
僕はプロダクトデザインを勉強していたんですが、その中で研究していたのが、装身具といって、義足や義手そういったものに興味があって。
それ自体は身につけて何かができるようになるという役割のものなんですが、リサーチしてみると、利用者の中には、そういう役割を求めるのではなく、こういったものがこういう形でついていたら格好いいんじゃないか、とかそういった理由で身につけている人も結構いるということがわかったんですね。なので何かの役に立つということを上回るぐらい格好いいとか、気分が高まるとか、誇らしく思える、みたいなことがあるなら、と学生の時に思い、プロダクトデザインが「役に立つこと以上に心を豊かにするもの」に興味を持ったんですね。
少し話が飛びますが、義手とかっていうのは失ったものを補うものじゃないですか。それを拡大解釈していくと、服っていうのは人間が体温調節できなくなったものを補うものだと考えて、プロダクトデザインとしての服を勉強し始めたんです。その延長にジュエリーというものが出てきまして、服で起こった体温調節をする機能がだんだんなくなっていって精神的に役に立つもの変化していったところまでをジュエリーでやってみたくなったんです。
現在は色々な活動をしているのですが、それと平行して家電であったり花瓶だったり腕時計などをデザインしたり、アートディレクションの仕事もしています。
例えば日本文化というものがどのように世の中に浸透していて、どのようにデザインされているか、どんな風に美しいものとして人に訴えかけているかということの背景を分析しています。
例えば海外の人が日本で何か作りたいとなったときにも、海外の文化と日本の文化をどのようなバランスで何と何を融合したら、今の時代に価値があるものになるのか?といった設計をして実装しています。
今回の展示では、ジュエリーでそれを純粋にやっているという内容ですね。基本的には現代において、どのようなものが美しいと思われているのか、価値があるのかな、どういったものを大切にしないといけないのかな、というものの象徴としてジュエリーをデザインしています。
それではコレクションの説明です。
UNBOUND
アンバウンドというコレクションです。
テープなど、何かを留めるものというのをモチーフにしてデザインをしているというコンセプトになります。
これは輪ゴムをモチーフにしたものから展開して種類が増えていっているのです。
どういった意図で作ったかというと、身の回りにある輪ゴムっていうのは本当にデイリーなものなんですけれども。普段は当たり前にあって皆気にもとめない、美しいかどうかということも考えないものですが、実は視点を変えると、これも美しいものなんじゃないかということを思っています。
日常にあって、普段から見慣れているものでも、見方を変えると、それは尊く美しいものなんじゃ無いかという価値観を提案しています。



細かいディティールの話になると、基本的には「幾何学の形を歪めて何かに見立てる」ということをしていて、例えばテープの場合は、四角の板が繋がって少しずれることでテープに組み立てられる。というようなことです。アンバウンドではそういうルールの中でデザインしています。
P:ディティールがとても美しいですね。この輪ゴムの形状のエッジの部分や磨きなど。
輪ゴムの場合は、1本の四角柱を作って職人の手で歪めて作っています。
椎:今の暖さんの今のお話ではどういった考え方で作っているかということでしたが、それを支えているのはやっぱりトップレベルの職人さんの技術というか、人の手だから生み出せるクオリティということにも向き合っていて。
暖:そいういう側面でいうと、現在は機械で切削していったり、3Dプリンター作るっていうこともある程度できてしまうわけですが、そういった中で職人の手でしか作れないものを作らないと意味がないんじゃないかと思っています。
これに関していえば、キャスト、いわゆる型を作っていて、金属を流し込んで量産することを指しますが、それは原型を3Dで削って、キャストにするための蝋に置き換え、蝋を金属に変えて作っています。これはその手法では絶対に作れないものを作っているわけなんです。

暖:例えばこれは0.2mm〜0.3mmの金属の板なんですけど、これを強度を保ってキャストするということ自体がそもそも無理なんですね。
それから、キャストで作った金属というのは中に細かい泡のようなものが入っていると考えてもらうとわかりやすいのですが、結構もろいんです。
なので、この薄さで仮にキャストで作ってしまうと、途中で折れたりフニャフニャになってしまって形を保てないんです。ですから、この鍛金(鍛金(たんきん)とは、金属を金床や烏口などにあて金槌で打つことで形を変えていく技法)で作ったものであれば、このデザインに形を留められるんです。
椎:その製法のどちらが優れているという優劣ではないんですが、それぞれ技法に得意分野がある中で、暖さんがこのアンバウンドの中で表現するものに向き合おうとした場合、この強度のある金属加工方法にたどり着いているというわけです。
暖:そうですね、このアンバウンドの場合は、キャストだとこの仕上がりのように磨くことができないんです。磨くと丸くなってしまって。
椎:やはり職人さんにもどう違うのかなど直接聞くわけですが、磨いていくときに作り手にはその差がはっきりわかるんですね。ピンと面が、角が出せると。
暖:世の中のジュエリーを見ると、やはりこういう角を出すというのは難しいんですね。角のデザインというのはあまりない。丸い曲がっていくデザインというのが殆どです。あれはやはり作り易いんですね。それが悪いということではなく、理にかなったデザインなわけです。そういう意味では理にかなっていないとも言えてしまうこの作り方を僕は格好いいと思っているんです。
P:では1本ずつ1から作っているんですか?
椎:そうです。1本ずつ金属の棒からつなげて。服で例えると、服を作るときには生地屋さんから生地を仕入れるようにジュエリーを作るときには地金屋さんというものがあります。その中でもレベルの違いがあって、ダンさんがブランド立ち上げのときからお付き合いのある地金屋さんは、世界でもトップクラスなんです。
先程お話したように日常のものが見方を変えるだけで美しく見えるように、これは丸に四角という非常にシンプルな形状なんですが、そこに日本トップクラスの職人の技術が加わることでジュエリーとして輝くわけですね。当たり前のことを丁寧にやることで、より美しさが際立つわけです。磨くという当たり前の技術を高レベルで行うことで美しいものに成り得るということが背景にあります。
椎:やはり面白いのはデザインの話もそうですが、これだけ思いを込めているのにそれが可視化されていないというのが、このジュエリーの魅力なのかなと思います。余白というか、見る人によってすごく見え方が違うんですよね。一番の強みというか、普通は自分がこれだけのことをやったというのをすごく残したくなるじゃないですか。それなのにそこは目立たせないにも関わらず、この四角い棒を歪めて輪にしているだけで、デザイナーの存在感を示しているというのはすごいです。
暖:家電などのプロダクトデザインにおいては、買ったときに一番価値があって、それがだんだん1年2年たつごとに目減りしていくじゃないですか。そういったものをデザインしているわけですが、ジュエリーって逆で、身につけてからだんだん価値が高まってくるっていうものだと思っているんです。それは自分の記憶とか思いとか、そういったものを蓄積していって自分にとって特別なものに変わっていくのがジュエリーだと思っていて。
なので、何かを留めるものをジュエリーだと思っていて、自分の思いなどを留めて、それを可視化することによって価値があるんじゃないかということ伝えたい、というのをこのコレクションで表現しています。
このコレクションは、「何かを留め、解き放つもの」というのをコンセプトとしていて、そこに集まってくる思いとか記憶とか価値観を身につけることで、より強くなったり、前を向けたりするっていうものでもあると思っています。何かを留めつつも、自分を開放していくような。そういうものであって欲しいと考えています。
このコレクションは、その何かを留めるものに見立てたものが少しずつ増えていくもので、これでこのコレクションが完成して、また新しいものを作るとかそういったことではなく、ずっと作り続けていくものです。
これは純粋に自分は輪ゴムのブレスレットを作るまでは、一個もジュエリーを身に着けていなかったんです。本当に欲しいジュエリーが見つからなくて、これを自分のために作ったというものです。
これを展示会で置いていたところ、これは良いからジュエリーブランドにしようというお声をいただいてスタートしています。きっかけは、本当にこれが1個だけ置いてあっただけなんです。(笑)

DISSOLVE
ディゾルブ
次に作ったのがこのディゾルブという今回のメインコレクションです。アンバウンドが当たり前のものを昇華させるコレクションだったものに対して、こちらはこれまでにない全く新しい革新的なことってどういうことができるんだろうということをテーマにしています。
ジュエリーで革新的なことをしようと思うと、新素材を作るか、新技術か、どちらかだと思ったんです。そこで僕たちは「新しい工芸技術を作ろう」という志のもと始まったコレクションで、試行錯誤のもと出来上がったものです。
背景にあるのが、イギリスの留学していたときに、大英博物館に行ったんですが、そこで古代ジュエリーが置いてあるコーナーがあって、すごく心惹かれたんです。後に煮詰めて、なんでそんなに惹かれたのかを考えると、表面に古代ジュエリーなどによくあるボコボコの凹みとか経年変化のディティールがあって、それ自体が持つ力が美しいと思わせているんだなと、それが新品であったとしたらそこまで惹かれなかっただろうなと思っていて、何千年とかの時間を経て付いた傷が力として宿っているんだろうなと。その傷っていうのを表現してみようというテーマで誕生したのがこのディゾルブです。
なんでこんな凹みや傷ができるんだろうというのを研究してくと、昔のジュエリーも金でできているんですが、今の金のようにピュアな金を生成する技術が発達してなかったんです。なので、金の中に他の金属が混ざっている。それが例えばピラミッドの下に埋もれていたり、土の中で何千年と経っていたりとかすると、金は経年変化しないんですが混ざっている金属は、経年変化するために侵食されて無くなっていくわけです。その抜けた金属の痕が、僕が大英博物館で見た古代ジュエリーの凹みだったわけですね。なのでその数千年経たないとできないテクスチャーというのを、現在の考え方で、ジュエリーの技法として作れないだろうかというのをディゾルブのコレクションとして開発しました。
まず金に異物が溶ける環境をあえて作り、数千年を待たずとも再現できるようにしたというのがこの技術の根幹です。


椎:このモデルも、半球を作ってから溶かしてこの形状になっています。ここにシルバーのモデルもならんでいますが、実はシルバーで同じものを作れるようになるまで3年を費やしているんです。
暖:そうですね。
P:最初に見せていただいた時は確かにシルバーはありませんでしたね。
椎:その時はまだできていなかったんです。
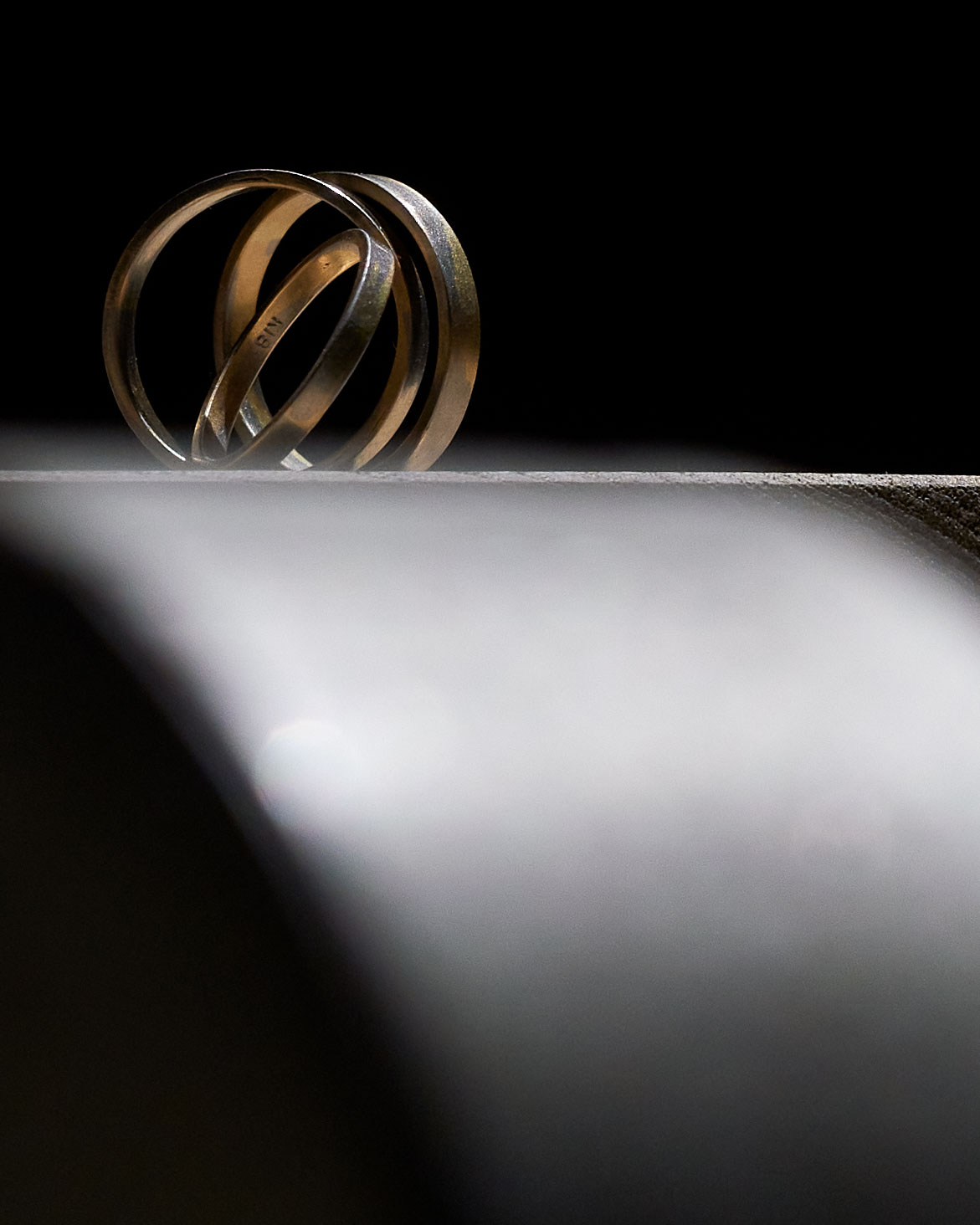

暖:これはディゾルブの一部なんですが、まだ溶かしていない状態のものです。
P:一旦全てこの形状になるんですか?
暖:そうですね。溶かす前の過程ですね。
混ざり方がそのとき1回限りなので、同じものはできないっていう意味でいうと、こちらは3Dで模様がでていますけど、こちらは平面で模様が出ているっていう兄弟みたいなものですね。この混ぜる技術も非常に難しいので。
P:これもリングになる前の状態は角棒なんですか?
椎:そうです。金属の混ざった大理石のような模様の棒をガンガン叩いて熱と圧力で形状を作ります。
P:これはキャストではできないですね。3Dに側面にも繋がって模様が出ていっているものになるので、これをキャストとか3Dプリンターでやるというのは難しいですね。
P:格好いい模様ですね。カモフラージュ柄のような感じですね。
椎:日本に昔からあるジュエリーに詳しい方だと、木目金(もくめがね)っていう技法があって、(今から400年前の江戸時代に生まれた、金属の色の違いを利用して木目状の文様を創り出す日本独自の特殊な金属加工技術)、刀の鍔とかに使われる技法なんですけど、金属の平面みたいなものを敷き詰めるんですよね。
金属のミルフィーユみたいな状態ですね。
そのミルフィーユの状態のものをグニャっとやって柄を作るんですね。年輪のような木目みたいな感じですね。それとはまた違った技術となります。
P:メッキというか、表面上の模様みたいな感じですね。
椎:DAN TOMIMATSUの場合はもっと有機的な表現ですよね。素材の特色を活かすという感じですね。
P:これも混ざっているんですか?
暖:そうです。自然光とかで見ると、不思議な色目に見えますよ。これはピカピカに磨いただけの状態ですね。ディゾルブは1つとして同じ柄がないので、並んだときにより面白さが際立つというか。

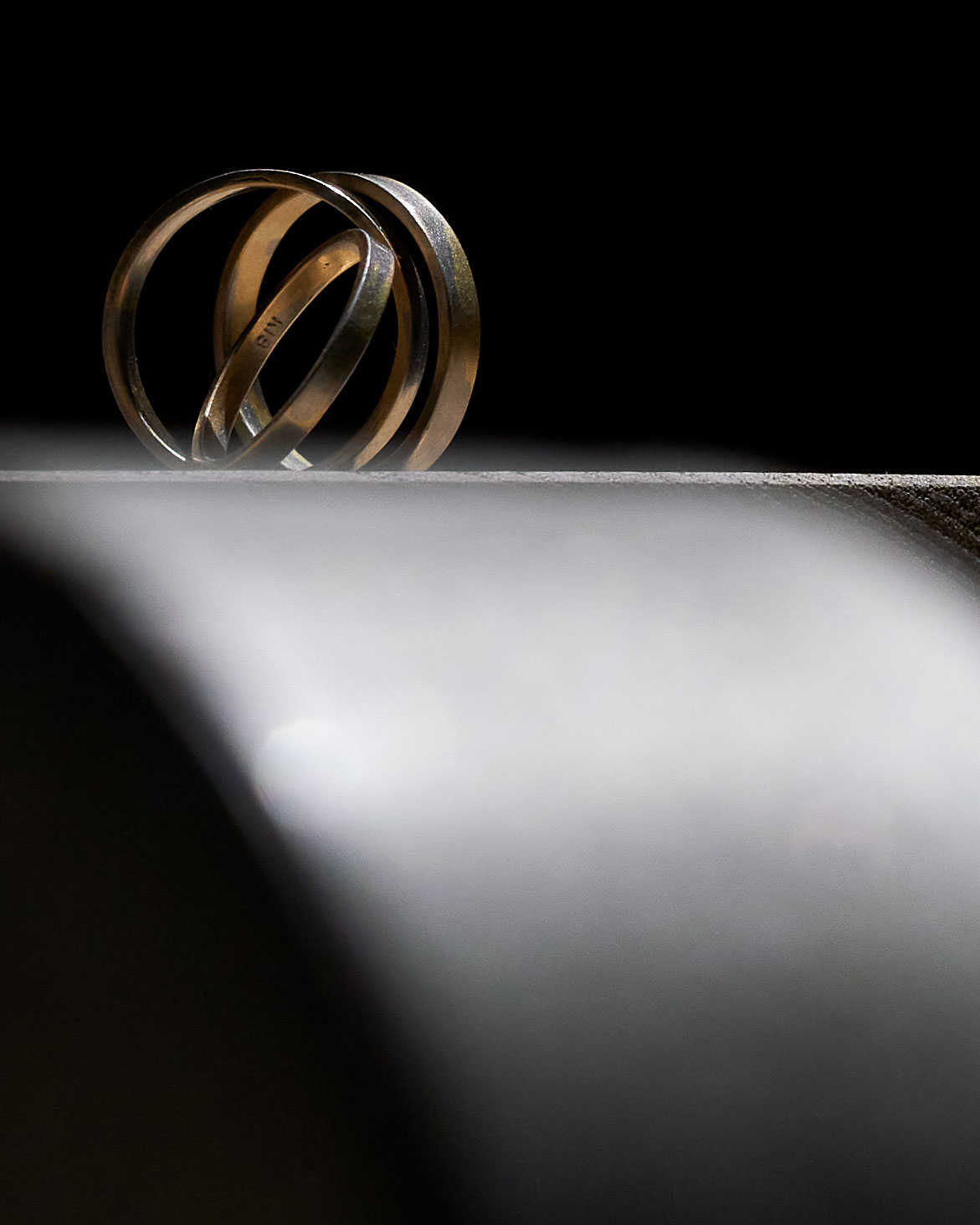
DEVRIS
デブリコレクション
椎:このピアスはデブリコレクションと言いますが、デブリというのは「塊」とか「欠片」とかそういう意味なんですが、用語的に面白いのは、「スペースデブリ」とか聞き覚えがあるかもしれませんが、惑星同士がぶつかったときにできる破片とかのことですね。これを先程の器の話しのように1つ1つ違う欠け方を見て自分にピンとくるものを探すような。沢山作ってズラッと並べたいよねという話しをしていました。

椎:溶かすのに1週間ぐらいかかって、溶け具合を見て、最後に仕上げる。職人さんと話していて、もやっぱり一番負荷のかかる工程で・・
暖:ドキドキしますよね。どうなってあがってくるかわからないので。もしかしたら何かが抜けすぎて割れちゃうんじゃないかとか、窯から出てこないと器がわからないのと同じで最後見るまで、どうなっているのかわからないんですよね。
椎:最後に仕上げを鏡面仕上げと、ルード(つや消し)フィニッシュから選んでいただけます。

ENLINK
エンリンク
暖:エンリンクというのは「何かをつなぎ合わせる」という意味なんですが、自分のルーツと現代をつなげるような試みをしてみようというコレクションです。
こちらは歴史とか、私は奈良育ちなんですが、そういう自分の過去とか地域の持っているものを見つめ直そうというプロジェクトからスタートしていて、日本では金糸っていうシルクに金箔が巻いてある糸があるんあるんですけれども。
坂:着物などで使われているものですよね。
暖:それで、その日本最古のものとして正倉院に収められているんです。それを見てみると金の無垢の金糸の細いものがあったんですね。それって何なのかを調べていくと、中国から伝来してきているものということがわかって、そこで中国へ行って、中国の金の糸を作っている人たちと一緒に金の糸の作り方を勉強して。ああこういったものなんだ、ということを理解してから作ったコレクションです。


暖:なので、革新的なことをするディゾルブをやった後に、自分のルーツを見つめ直すわけじゃないですけれども、そういったところからデザインを起こして、このenlinkというコレクション作っています。

P:日本にそういう糸を作っているところはなかったんですか?
暖:シルクに金箔を巻くタイプの金糸を作っているところは数店舗ぐらい残っているんですが、それもだんだん減っていっていて、今はもうフィルムを巻いて、その上に金メッキをしたものが殆どなんです。本物の金箔を巻いているところは京都に1店舗あるのを知っています。
P:その糸のもとを辿るとこの糸になるんですか?
暖:その当時は2パターンあったようで、シルクの糸に金箔を巻くタイプと、無垢のワイヤーみたいなものに取り付けるパターン。それで細いワイヤーの方の作り方を研究して、実際現地に行って作ってやっているわけです。
椎:バングルなどもそうですけど、新しい技法に取り組むというよりも、歴史とかそういうものをデザイナーという背景も含めてモダンに表現している感じです。あとは、ブランドとして初めて異素材の組み合えせというのを初めて
やったのがこのエンリンクコレクションです。最初はシルバーとゴールドだったんですが、このときゴールドとゴールドでやりたいよねという話しをしていて、取り組んだんですね。
暖:エンリンクは何かを留めるものとして、0.1mm-0.25mmの金糸を作って縫い止めるっていうのがコンセプトになっています、
ちょっと穴があいているじゃないですか。そこを金の糸でジグザクに縫っているんです。これがエンリンクとアンバウンドの架け橋になるような存在です。
SILK ROPE
シルクロープ
シルクロープもそんな流れの中のひとつのようなところがあります。
これは京都の着物の帯などに使われている組紐を使ったコレクションになります。
京都の老舗組紐職人さんに作ってもらっています。組み方や、糸の本数、仕上げの風合いを産むための加工など、綿密に打ち合わせを重ね、製作しています。伝統的にあったものを僕の感性と現代的な解釈で表現しています。
組紐も、着物文化が衰退しつつある中で、新しいアプリケーションを見つけなければ、生産量が減りいずれ無くなってしまう文化かもしれません。
かと言って、無理に何かを組紐で代替してみるような解を出すのではなく、
組紐は組紐として、価値のあるとのとして、現代の生活に馴染むアウトプットを目指しています。
組紐自体が持っている特性や美しさを変えてしまう事なく、私が新たにデザインしたジュエリーと組み合わし一体化させる事で、違和感なく、現代人が日常で身につけられるものになるようデザインしました。


まだまだ、細かい部分でのお話は尽きることが有りませんが、大まかには以上が今回展示させて頂いているコレクションの説明になります。
お話ししましたようにジュエリーを生み出す上で、考えていることが少なからずあります。
私が、人類が作り上げて来たジュエリー文化を知り、見て、着けて感じたことをDAN TOMIMATSUで表現したように、身に付けて下さった方がどのように感じられるのか言う事こそが、一番大切な事だと思っています。
作り手の思いというのは、いったんジュエリーが完成してしまえば、目の前にあるジュエリーの背景に過ぎないと思っています。
私たちが制作したジュエリーを身に付けて頂き、少しでも生活にご一緒出来ることがあれば幸いです。



